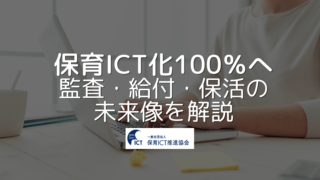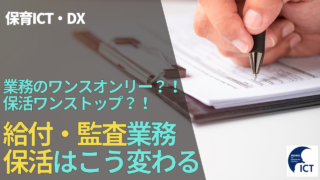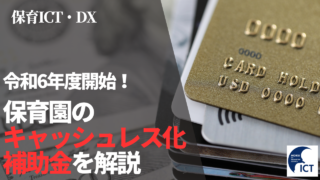こんにちは、保育ICT推進協会の三好です。
保育のICTを導入したものの「業務に結びついていない」「効率化できている実感がない」と感じている方も多いのではないでしょうか?
先日、以下のようなご質問をいただきました。
「私は保育園で主任をしています。最近ICTを導入して使い方にも慣れてきたのですが、業務にはなかなかつながっていません。また、園長や他の職員も業務の見直しにはあまり積極的ではなく、私自身もどこをどのように改善していけばいいのか分からず悩んでいます。どのように進めればよいでしょうか?」
このように、ICTを導入したものの、実際の業務改善に結びつかないという悩みは多くの保育現場で見られます。そこで、本記事では**「どこから業務を見直せばよいのか?」**という初めの一歩について、具体的なポイントを詳しくお伝えしていきます。
この記事の内容はYouTubeでも解説しています。
厚生労働省のガイドラインを参考に

まず、業務改善の進め方として参考になるのが、「保育分野の業務負担軽減・業務の再構築のためのガイドライン」です。
このガイドラインはこども家庭庁のホームページでPDFが公開されており、誰でもダウンロードできます。
このガイドラインでは、業務の効率化を図るためのステップが整理されており、園全体で取り組む際の手順が示されています。
しかし、ガイドラインの内容は、すでに園全体が業務改善に前向きな場合に適用しやすいものとなっています。
今回のご質問のように、園長や他の職員が業務改善に消極的な場合、いきなりガイドラインの手順を適用しようとしても難しいことがあります。
そのため、まずは「日常業務の中で見直しやすいポイントを探す」方法を今回は考えてみましょう。
業務見直しのポイント3選
1. 「これやっとくと安心だから」という仕事
「これをやっておけば安心だから」という理由で続けている業務がないか見直してみましょう。
例:ICT導入後も手書きで並行管理している
- ・すでにICTシステムで登降園時間を記録している
- ・でも、「打刻し忘れがあると不安だから」と、手書きの出席表も併用している
一見するとミスを防ぎ安全管理にも役立ちそうですが、ここで大切なのは下記の2点です。
- ミス(打刻忘れ)はどれくらいの頻度で発生しているか?
- 週に何回起こるのか
- どの保護者に偏っているのか
- ミスが起こるとどの程度のリスクや影響があるのか?
- 保育に大きな支障が出るのか
- 保護者や担任が後から入力するなどで十分カバーできるのではないか
「打刻忘れが月に数回で、かつ保育上のリスクや費用トラブルに大きく直結しない」のであれば、“安心のために”毎日全員分を二重管理するのは、業務の労力に見合っているのかをもう一度考える余地があります。
「やっとくと安心」という業務は多くの場合、リスクに比べて業務負荷が大きすぎることがあるので要チェックです。
2. 「私がやったら終わるから…」で済ませてしまう仕事
保育園の会議などで何か新しいタスクが発生した際に、よくある流れが
「私がやっとくね。私がやればすぐ終わるから」
というものです。あるいは
「あの先生がいつもやってくれるからお願いしよう」
というケースも要注意です。
例:消耗品の注文が特定の先生だけの“ブラックボックス”に
- 「注文はあの先生が詳しいから任せっぱなし」
- 「どのタイミングでどこへ依頼しているか誰も把握していない」
こうした状況は、業務の「俗人性(ぞくじんせい)」 につながります。
俗人性とは、「その人がいないと業務が回らない状態」 のこと。
保育の“子どもとの関わり”自体は、担任の個性や良さを生かすためにもある程度の“俗人性”が必要です。しかし、注文や書類管理などの事務的業務が一人にしか分からない状態は、園全体にとって大きなリスクです。
1人の先生が休んだり退職したりすると回らない…というのでは組織として成り立ちません。
- 「この業務は園としてどう進めるべきか」
- 「全員が同じ情報を共有するにはどうすればよいか」
など、特定の先生だけの仕事にしないしくみづくりが必要です。
3. 「他の園ではやってないみたいですよ」という情報
「うちの園ではやっているけど、他の園ではやっていない」と言われる業務があれば、見直しのチャンスです。
例:特定地域だけで運用されていた個人カルテ
- ・園児の内科検診、歯科検診、身体測定、何歳何ヶ月検診などの結果をすべて書き写して、一人ひとりのカルテ形式でまとめている
- ・実は他の地域では園全体で一括管理するだけでよく、個別に書き直す必要はない場合も
このように、他の園でやっていない理由 を調べてみると、
- 本当にその業務自体をやっていない
- 別の業務でカバーしている
に分かれることがあります。また、そもそもそれが
- ・いつ、どういう理由で始まった仕事なのか
- ・法令上、本当に必要な書類なのか
を確認すると、実は園独自で「慣習的に」続けていただけだった…というケースも珍しくありません。
「他園ではやっていない」は、単なる噂話として終わらせず、自分の園の業務を客観的に見直すチャンスとして捉えてみましょう。
3. まとめ:まずは“気づき”をきっかけに小さく始める
今回ご紹介した
- 「これやっとくと安心だから」
- 「私がやれば終わるから(俗人化)」
- 「他の園ではやっていないみたいですよ」
この3つのポイントに該当する仕事や書類があれば、業務改善のチャンスです。ガイドラインどおりに大がかりなプロジェクトを立ち上げなくても、まずは保育士・職員それぞれが日々の業務のなかで
- 「本当に必要か」
- 「誰が、何のためにやっているか」
- 「リスクとコストのバランスは取れているか」
を意識してみてください。そこから“ここは省けるかも” “ICTで自動化できるかも”という具体的なアイデアが湧き上がることがあります。
当協会では、保育施設のICT活用支援や、自治体向けの巡回伴奏支援を実施しております。業務改善やICTの活用に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。